

千葉のファーメンステーションが東京大学と共同研究を開始し環境価値の測定を目指す
千葉のファーメンステーションと東京大学の共同研究
千葉県船橋市に本社を置く株式会社ファーメンステーションは、東京大学の未来ビジョン研究センターおよび先端科学技術研究センターと共同で、新たな研究プロジェクトを開始しました。この共同研究は、バイオものづくりを通じて未利用資源の再生・循環を目指すもので、特に発酵技術の環境に対する影響を定量的に評価するフレームワークの確立を狙いとしています。
1. 環境問題へのアプローチ
昨今、気候変動や資源循環の必要性が高まっています。当社の目的は、未利用バイオマスの活用を通じて、廃棄物を削減し地域資源を有効活用することです。発酵技術を用いて、コーヒー粕や米ぬかなどの未利用資源から高付加価値な素材を生み出す可能性を秘めています。しかし、現時点では発酵素材の環境負荷を広範囲にわたって測るフレームワークが十分でないのが現実です。
2. 共同研究の目指すもの
本研究では、当社が保有する発酵アップサイクル素材の候補を出発点にしながらも、個別製品に留まらず、未利用バイオマス発酵プロセス全般が対象です。連続的なライフサイクルアセスメント(LCA)を行い、原料調達から発酵、製品化、副産物利用に至るまでのプロセスを包括的に分析します。この過程での優位性を数値化し、従来のシナリオとの比較を通じて科学的に証明することを目指します。
3. 社会的要請を見据えた研究
2030年、2050年といったカーボンニュートラル目標や国際的な持続可能性の基準に基づいた認証制度に向けて、将来の社会要請を見越した設計要件を取り込むことで、事業の持続可能性を高めていきます。また、地域特性を活かした製造・循環シナリオを描き出すため、柔軟な事業モデルの構築も重要なポイントです。
4. 研究成果の実用化
この研究成果は、食品メーカーや自治体との協力によって社会実装を図り、国際市場への展開を目指します。ファーメンステーションとしては、環境価値を重視した新たな産業モデルの形成を急ぎます。
5. 共同研究者の紹介
このプロジェクトには、東京大学から菊池康紀教授と小原聡特任教授が参加しています。菊池教授はライフサイクル工学の専門家として、資源循環やエネルギーの領域で多面的な研究に取り組む一方で、小原教授はバイオプロセス工学の専門家として発酵技術の評価を行っています。
6. 将来の展望
ファーメンステーションは、農林水産省のSBIRフェーズ3事業とも密接に連携し、量産実証で得たデータを活用することで、研究成果を事業化へとつなげます。また、確立したLCA手法を基に、多様な事業モデルの実現を視野に入れることで、地域資源を最大限に活かした市場の創出に注力します。
7. ファーメンステーションのビジョン
当社は「Fermenting a Renewable Society(発酵で楽しい社会を!)」を掲げ、持続可能な未来の実現に向けて、未利用資源を新たなバイオ素材に転換する活動を展開しています。今後とも「味や機能性」と「環境的価値」との融合を進め、より良い社会の形成に寄与していく所存です。
詳細な技術情報はこちらからご覧いただけます。

関連リンク
サードペディア百科事典: 東京大学 ファーメンステーション 環境技術
トピックス(グルメ)

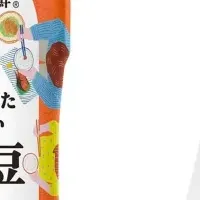








【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。