
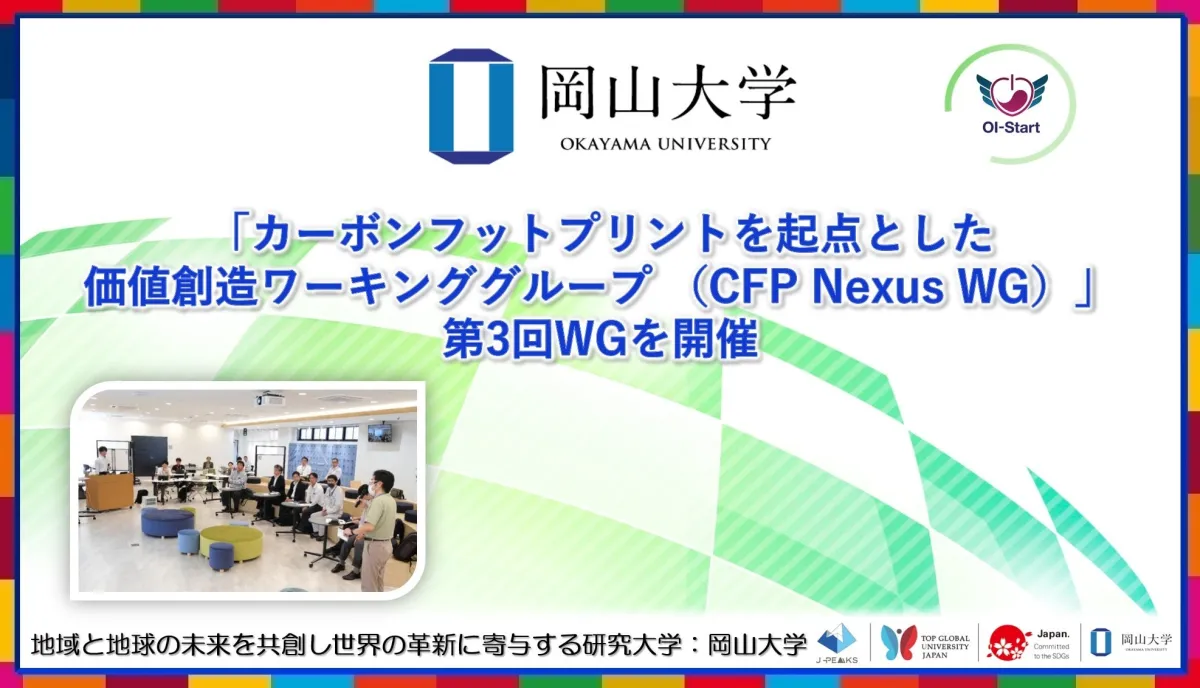
岡山大学がカーボンフットプリントを基にした価値創造の取り組みを進展
岡山大学が推進するカーボンフットプリントの価値創造
国立大学法人岡山大学は、2025年11月5日に「カーボンフットプリント起点の価値創造ワーキンググループ(CFP Nexus WG)」の第3回ワークショップを共創イノベーションラボKIBINOVEで開催しました。この取り組みは、地域企業の競争力を強化し、グリーントランスフォーメーション(GX)の実現を目指して、産学官金が連携して行われています。
当日は約40人が参加し、企業関係者や研究者、学生、金融機関が一堂に会しました。ワークショップの冒頭では、新しいメンバーの紹介が行われ、岡山大学研究・イノベーション共創機構の舩倉隆央副本部長からは本ワーキングの背景と目的について説明がありました。参加者は、カーボンフットプリントが地域社会にどのように影響を与えるかを熱心に議論しました。
次に、中電環境テクノス株式会社から高田舜也氏が登壇し、同社が提供する脱炭素支援サービスを紹介しました。高田氏は、企業の省エネ診断やCO₂の可視化、SBT認定支援など、幅広いサービスを通じて、地域企業との連携を強化している点を強調しました。また、岡山大学が推進する「カーボンフットプリントチャレンジ」にも積極的に関与していることが印象的でした。
さらに、岡山大学の経済学部からは天王寺谷達将准教授が発表し、岡山県商工会連合会やシバムラグループと連携して進めている「カーボンフットプリントチャレンジ」の詳細や、株式会社サンラヴィアンとのCFP表示に向けた取り組みについて報告しました。これらの活動は地域の脱炭素化に向けて具体的な成果を上げています。
ワークショップの最後には、舩倉副本部長が「消費者にとってわかりやすいCFP表示の在り方」をテーマに議題を提供し、参加者たちが活発に意見交換を行いました。この議論を通じて、単なるCO₂排出量の算定にとどまらず、CFPを出発点とした新たな価値創造に向けた動きが強化されていくことが明らかになりました。
岡山大学は引き続き地域企業や支援機関とともに、より実践的な脱炭素化とイノベーションの推進に取り組む意向を示しています。地域中核・特色ある研究大学としての岡山大学の活動は、地域社会における持続可能な発展に向けた重要な一歩といえるでしょう。
カーボンフットプリントは、製品やサービスのライフサイクル全体を通じて排出される温室効果ガスの排出量を可視化する手法です。この技術が普及することで、企業だけでなく消費者も環境意識を高め、引いては社会全体の脱炭素化に貢献することが期待されています。今後も岡山大学の新たな試みから目が離せません。
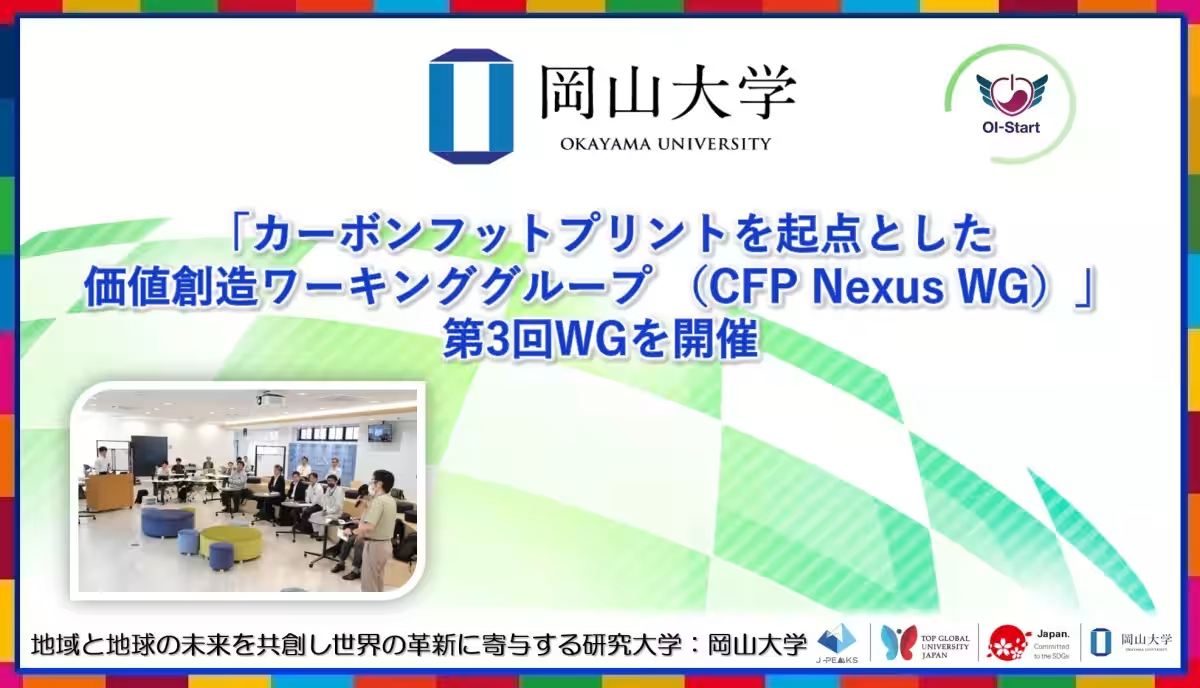







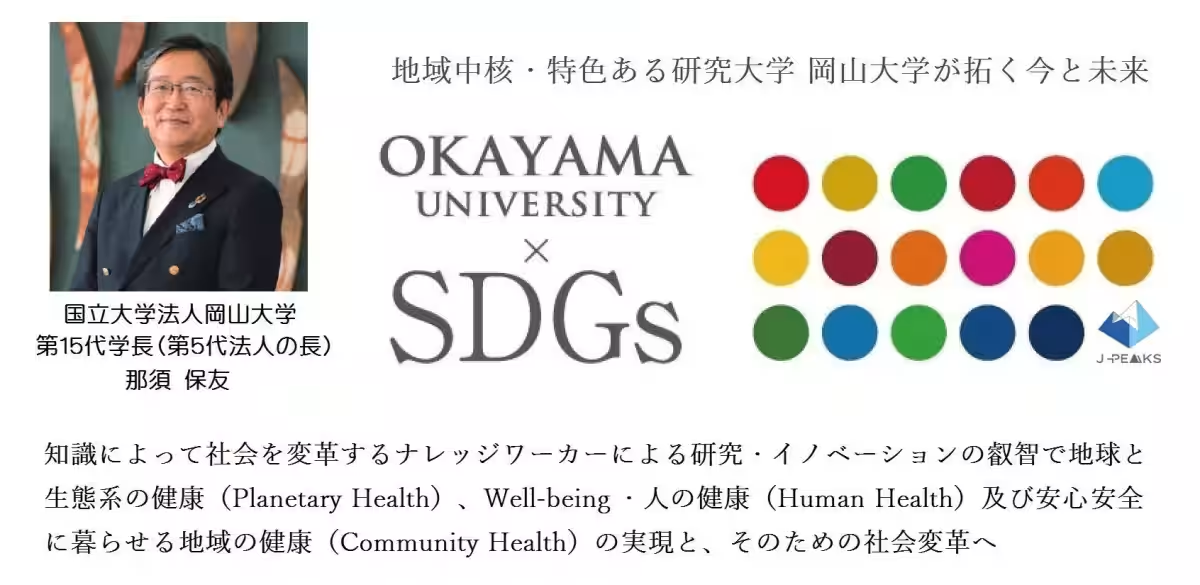

関連リンク
サードペディア百科事典: 岡山大学 カーボンフットプリント 地域企業
トピックス(その他)



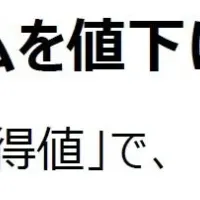


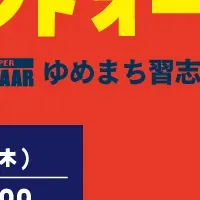



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。