

次世代モビリティを支える!小野測器と東京大学の連携の取り組み
次世代モビリティ開発の最前線
千葉県柏市に位置する東京大学柏キャンパスで、小野測器と東京大学との共同研究が発表されました。この双方の協力による「電気自動車の振動計測制御に関する社会連携講座」は、2022年に設置され、次世代モビリティの発展に寄与するプロジェクトが進行中です。
代表取締役社長の大越祐史氏、東京大学の藤本博志教授、そして他の関係者が参加したこの発表会では、研究の成果と今後の取り組みが詳しく説明されました。特に注目されたのは、2026年からスタートする第2期活動に向けた「自動車用試験装置の制御に関する研究」です。
第1期活動の成果
第1期活動は2022年から2026年にかけて行われ、主に電気自動車の振動抑制制御に焦点を当てていました。この活動を通じて、電気自動車の「乗り心地の向上」に貢献することが目的とされ、多くの試験が東京大学の柏キャンパスに設置された「RC-S 実車トランジェントベンチ」を用いて実施されました。これにより、実際の道路環境に近い条件下での実験が行われ、より実践的な研究が進められました。
第2期活動の進展
来る2026年4月から始まる第2期活動では、1期の研究を継続しつつ、自動車用試験装置の制御技術の開発が新たなテーマとして加わります。この装置は、愛知県の新拠点「中部リンケージコモンズ」に導入され、次世代モビリティ技術の実現に向けた重要な拠点となる予定です。
小野測器の役割とビジョン
小野測器は、1954年の創業以来、電子計測器の開発と製造において先駆的な役割を果たしてきました。特に、自動車産業における測定技術の提供と研究支援に注力しており、教育機関との連携を通じて次世代技術者の育成にも力を入れています。また、地域社会との関わりを重視し、地域の子どもたちとの協力活動なども実施しています。
まとめ
小野測器と東京大学の取り組みは、自動車産業における未来の技術革新に寄与し、持続可能な社会の実現を目指しています。今後も研究活動によって、より良い「乗り心地」が提供されることに期待が寄せられています。この活動は、単に自動車技術に留まらず、自動運転車やドローンといった新しいモビリティ技術の開発へもつながる可能性を秘めています。



トピックス(その他)

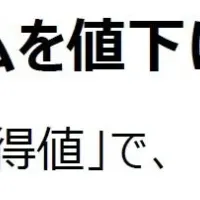


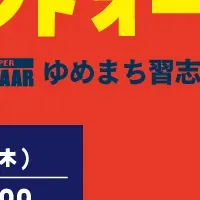



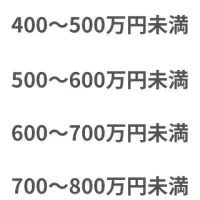

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。