
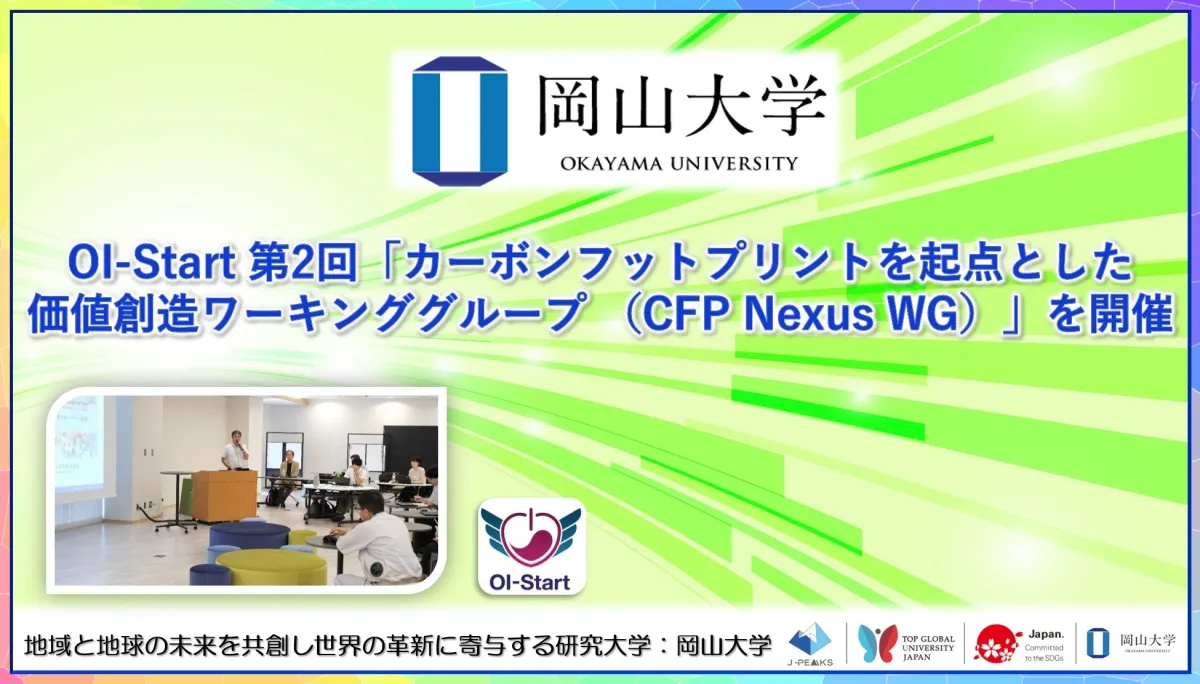
岡山大学が主導する脱炭素の新たな取り組みと地域の価値創造とは
岡山大学が主導する脱炭素の新たな取り組みと地域の価値創造とは
岡山大学は、国立大学として持続可能な社会に向けた取り組みを強化しています。特に注目されるのは、カーボンフットプリント(CFP)を起点とした「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム(OI-Start)」が開催する産学官金連携のワーキンググループ、CFP Nexus WGです。このプラットフォームは、地域企業の競争力を高め、グリーントランスフォーメーション(GX)を実現するための新しい価値創出を目指しています。
ワーキンググループの開催
2025年7月31日、岡山大学の津島キャンパスにある共創イノベーションラボKIBINOVEにて、第2回のCFP Nexus WGが開催されました。この日は約50名の参加者が集まり、企業の代表者や研究者、学生、金融機関の関係者が一堂に会し、意見や情報を交換しました。特に注目を集めたのは、株式会社メタルワン菱和の流田龍扶社長のスピーチです。
流田社長は、鉄鋼流通業におけるカーボンニュートラルへの取り組みについて語りました。同社では、電力量の可視化システムを導入し、省エネ運転の推進や設備の稼働時間の見直しなど、具体的な成果を挙げています。着実に年間4万kWhの電力削減を実現しており、地域に貢献できる企業を目指す姿勢が印象的でした。
環境価値を高める新しい提案
次に、一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)の仲井俊文氏が、「サーキュラーエコノミー(CE)×脱炭素支援パッケージ」の提案を行いました。彼は顧客ごとの非効率な在庫や設備についての課題を挙げ、設計や管理の面から「共有化・汎用化」を進め、環境負荷とコスト削減の両立を図るアイデアを紹介しました。
特にCFPと資源の循環性を評価するCE指標の組み合わせにより、商取引先に対しても環境価値を付加できるという提案は、地域企業へ大きな影響を与えるでしょう。
中小企業への支援ツール「CORD」
続いて紹介されたのは、同機構の今後舞氏による中小企業でも利用しやすいCFPやライフサイクルアセスメント(LCA)のための排出原単位データベース「CORD」についてです。このツールは専門知識がなくても扱いやすいことが特徴であり、LCAやスコープ3の評価にも役立つため、参加者の関心は非常に高まりました。
今回のワーキンググループでは、単なるCO2算定にとどまらず、CFPを基にしたビジネスモデルの変革や新たな価値創造への道筋が示されました。岡山大学は今後も地域企業や支援機関と一緒になって、実践的な脱炭素化やイノベーションを推進していくそうです。
期待が高まる岡山大学の取り組み
岡山大学のCCI(共創イノベーション)の取り組みは、地域の中核的な研究機関としてますます重要性を増しています。持続可能で魅力的な地域社会の実現に向けて、今後もさまざまな新しい試みが期待されます。
各方面の専門家や学生たちが集まり、相互に学び合いながら新たな知見を得る機会がこのように増えていくことで、岡山地域全体がさらに活性化し、持続可能な未来へとつながっていくでしょう。地域中核・特色ある研究大学としての岡山大学の取り組みには、今後も注目が集まります。
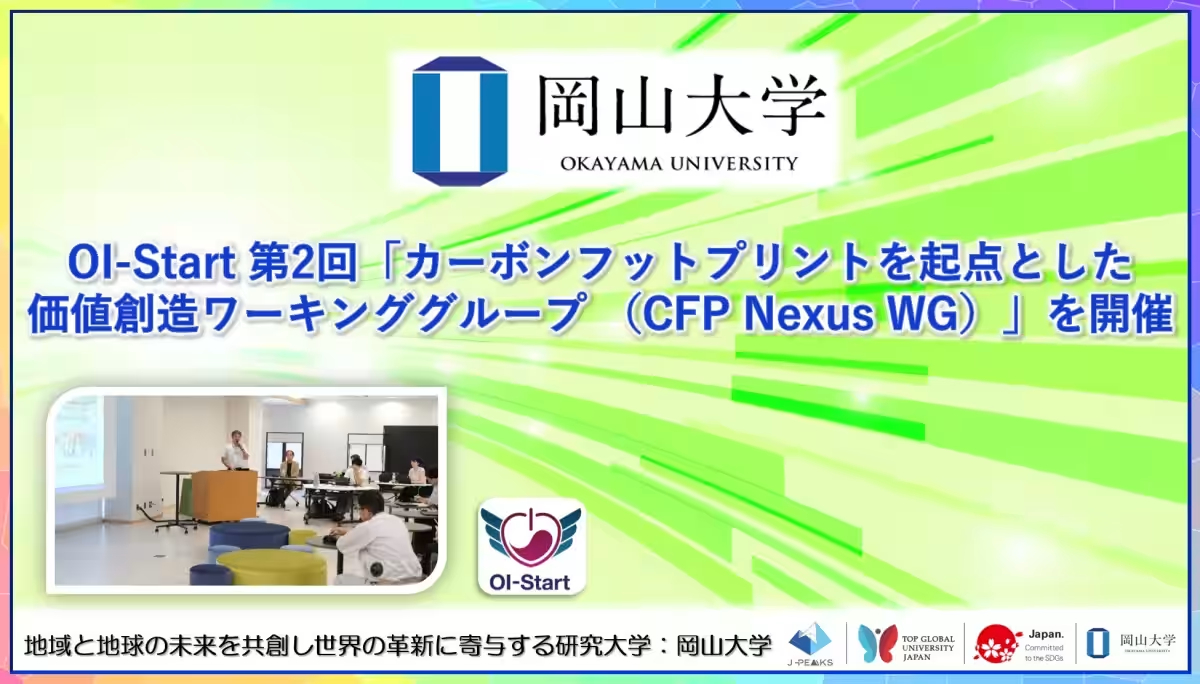










トピックス(その他)





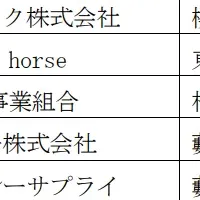

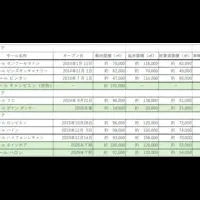
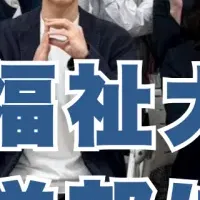

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。