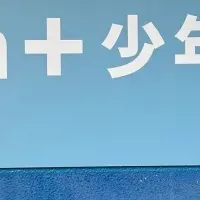

くら寿司と海と日本プロジェクトのコラボ授業、『お寿司で学ぶSDGs』のご紹介
くら寿司と海と日本プロジェクトが共催する出張授業
一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねは、2025年11月13日(木)に宍道小学校で、くら寿司株式会社と共同で「お寿司で学ぶSDGs」という特別な出張授業を実施します。これは、次世代を担う子どもたちが海洋環境や食品ロス、そして低利用魚の重要性について学ぶことを目的としたプログラムです。全国的に人気を誇るこの授業が、島根県で行われるのは今回が初めての試みです。
授業の背景と目的
近年、漁業資源の減少や食品ロスの問題など、私たちの日常に深く影響を及ぼす課題が増えてきています。この授業を通じて、児童たちが「海の恵み」を未来に引き継ぐために何ができるかを考える機会を提供します。授業は、SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」、目標14「海の豊かさを守ろう」、と目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に基づいて構成されており、実践的なアプローチを取り入れています。
授業内容の詳細
この出張授業では、複数のアクティビティを通じて、子どもたちが楽しみながら学ぶことができるように設計されています。
1. 隠岐体験学習の振り返り
まず、海と日本プロジェクトinしまねによる「隠岐めしと歴史探険隊」の活動を振り返ります。このプログラムには、山陰両県の小学5・6年生が参加し、隠岐諸島での体験学習を通じて地元の歴史や漁業の現状について学びました。特に、隠岐の海産物がどのようにして歴史的に重要であるかを理解し、地元の漁師から獲れたての海産物の扱い方を教わる貴重な機会でした。実際に郷土料理を作る工程を経て、海の豊かさとその保護の重要性を学ぶことができるのです。
2. お寿司屋さん体験ゲーム
続いて、くら寿司が開発した「お寿司屋さん体験ゲーム」を通じて、子どもたちは実際に寿司を作る楽しさとともに、過剰提供や廃棄の問題を体感します。この体験では、食材の大切さや資源の管理の重要性を肌で感じることができ、未来への意識を高める絶好の機会になります。
3. 解決策を考えるワークショップ
最後に、子どもたちはグループで意見を出し合い、どのようにしてお寿司を未来にも楽しめるかをテーマに討論します。この部分では、ICTを活用した食品ロス対策や低利用魚の利用促進に関する具体的なアイデアを考え、発表します。子どもたち自身の創造性を活かした解決策の提案は、将来の持続可能な社会を築くための重要な要素となります。
今後の展開
このプログラムは、宍道小学校以外にも松江市内の複数の学校で行われる予定です。教育関係者や保護者たちにも注目されるこの活動は、次世代の意識を高め、地域社会全体で海の保護に対する理解を深めることに繋がるでしょう。
美しい日本の海を未来に引き継ぐためには、今、私たち一人一人ができることを考え、行動することが重要です。くら寿司と海と日本プロジェクトのコラボ授業が、小学生たちにとっての新しい学びの場になることを期待しています。
取材案内
この授業に関連した商品や低利用魚の活用について興味があるメディアの方々は、くら寿司 松江店での取材も受け付けています。出張授業当日は、授業前にメディア向けのレクチャーも予定されているのでぜひご利用ください。
まとめ
ぜひ2025年11月13日、宍道小学校での「お寿司で学ぶSDGs」にご注目ください。これからの海の未来を自分ごととして考える機会になります。持続可能な社会を目指すためには、子どもたちの発想力を育てることが大切です。この取り組みが、その一助となることを願っています。



関連リンク
サードペディア百科事典: 海と日本プロジェクト SDGs くら寿司
トピックス(イベント)
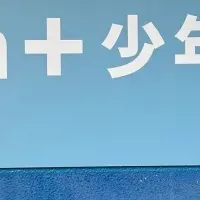
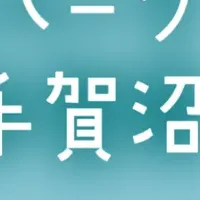
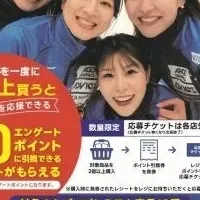






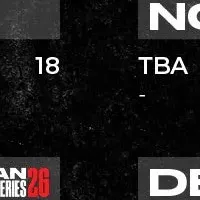
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。