

鮭の日に祝う!サーモン寿司誕生40周年の魅力
鮭の日に祝う!サーモン寿司誕生40周年の魅力
食欲の秋が深まる11月11日は、「鮭の日」。この日は、回転寿司で人気のサーモン寿司が誕生してからちょうど40周年を迎える記念の日でもあります。多くの記念日がある中で、鮭の日の誕生背景や、回転寿司界におけるサーモンの地位について詳しく見ていきましょう。
11月11日、鮭の日の由来とその意味
一般社団法人日本記念日協会によって認定された「鮭の日」は、漢字の「鮭」の形が「十一」の数字と似ているところに由来していると言われています。秋は、サツマイモや栗、キノコなども旬を迎える時期で、食欲が増す季節です。この日に合わせて、回転寿司で盛り上がるサーモンの魅力を振り返るのは、実にタイムリーなのです。
サーモン寿司の40年の歴史
1980年代、日本にノルウェーからサーモンの輸入が始まり、それが回転寿司業界に革命をもたらしました。サーモンはその鮮やかなピンク色と食べやすさから、瞬く間に人気のネタとなり、食文化に大きな影響を与えました。特に、回転寿司の登場は、家族連れや子供たちにもサーモンの魅力を広め、世代を超えて愛される存在となりました。最近の消費者調査でも、サーモンは14年連続で首位を獲得しており、その人気は不動と言えます。
養殖と新たな試み
サーモンはほとんどが養殖で育てられていますが、近年では国内でも養殖の動きが活発化しています。特に三陸や九州沿岸での「海面養殖」にとどまらず、陸上で魚を育てる新たな「陸上養殖」プロジェクトが進められています。人工的に水質や環境を制御できるため、海に近くない地域でも養殖が可能です。また、この方法は水の浄化や節水にもつながると期待されています。
地域ブランドサーモンの創出
地域ごとの特色を活かしたご当地サーモンも注目されています。青森県の「海峡サーモン」や兵庫県の「神戸元気サーモン」、さらには果物を使った「みかんサーモン」や「レモンサーモン」も誕生しています。これらの地域ブランドは新たな雇用の創出に寄与し、地域経済にも貢献しています。サーモンの養殖は、技術革新と地域密着型の取り組みにより進化を続けています。
ノルウェー大使館とのインタビュー
日本とノルウェーの外交関係樹立120周年、そしてノルウェーサーモンの日本上陸40周年を迎えるにあたり、ノルウェー大使館の水産参事官ヨハン・クアルハイム氏にインタビューを行いました。彼は、1980年代に日本市場に注目した理由として、生食の需要が高い日本にプロジェクトを立ち上げ、回転寿司とのコラボレーションが、ノルウェーサーモンの普及に貢献したと語っています。
未来に向けた展望
現在、ノルウェーサーモンの消費は増え続けており、骨抜きされて簡単に利用できる点が支持されています。発売から40年が経過した今も、様々な形で日本市場に向けて新たな取り組みがなされています。くら寿司では、「函館サーモン」や「みかんサーモン」などの新商品も開発しており、今後の期待が高まります。
今後もサーモンの人気は続くことでしょう。11月11日に、ぜひ鮭の日を祝って、サーモンの美味しさを再確認してみてはいかがでしょうか。新しいサーモンを探して、家族と一緒に楽しい食卓を囲むことをおすすめします。










トピックス(グルメ)

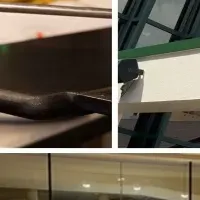







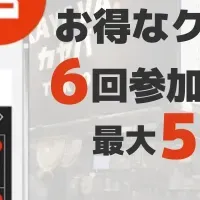
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。